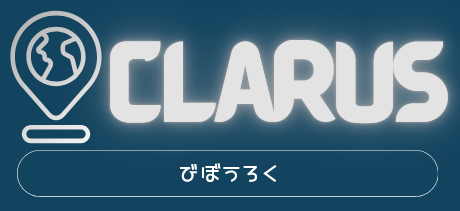受験の経緯
昨年も受験しましたが、科目Bで点数が足らず不合格でした。今回はこれから職場でPM職を担当することになるので、改めて「共通言語を増やしてスムーズな合意形成に至ること」をメインの目的としてFE試験を再受験します。
基本情報技術者試験の概要
FE試験の概要と特徴
- 略号: FE
- 主催: 情報処理推進機構(IPA)
- 資格の種類: 国家資格
- 対象者像: 高度IT人材となるために必要な基本的知識・技能を持ち、実践的な活用能力を身に付けた者
- 試験形式: CBT(Computer Based Testing)方式。コンピュータを使って受験する形式で、全国のテストセンターで随時受験できます(年末年始を除く)。
- 試験時間と科目:
- 科目A(旧午前試験): 90分、多肢選択式(四肢択一)60問。テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系の幅広い分野から出題されます。
- 科目B(旧午後試験): 100分、多肢選択式20問。アルゴリズムとプログラミング(Python, Java, C, アセンブラ, 表計算から選択)、情報セキュリティ、データ構造とアルゴリズムに関する問題が出題されます。
- 合格基準: 科目A、科目Bともに1,000点満点中600点以上の獲得が必要です。
- 受験料: 7,500円(税込)
- 受験資格: どなたでも受験可能です。
ちなみに、「科目A免除制度」という魅力的な制度がありますが、今回は利用しません。
利用しない理由は2つあり、免除試験の受験時期が【6月・7月/12月・1月】となっておりタイミングが悪いこと、また、費用がかかることです。
前回受験した時は科目Aは800点ほど取れたので、今回も科目Aはしっかり勉強していれば大丈夫なはずです。
新シラバスver9.0
受験時期がずれると、シラバスが改定され出題範囲が大幅に変わります。
2024年10月に新規追加された新シラバスで扱う単語の総まとめ動画を見つけました。圧倒的感謝です。
IT資格の動画解説でおなじみのすーさんも新シラバスの動画を出してくれています。
学習プラン
受験日は2025/08/30としました。
学習期間は【2025/07/09~2025/08/30】とします。
参考書流し読み 約10日間(~7/20)
まずは参考書を通読して全体像を頭に入れます。
使用する参考書は『【令和7年度】 いちばんやさしい 基本情報技術者 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ)』
以前はキタミ式で学習したので、今回はこちらの参考書で違った角度から学習してみます。
苦手単元の理解 約10日間(~7/30)
参考書を通読する中で苦手な単元を把握し、その単元を動画学習や集中的に学習します。
過去問・シラバス演習 約30日間(流し読み終わり次第着手)
おなじみの「過去問道場」で何度も周回します。
新シラバスの問題にも取り組みます。
科目B対策 約50日間(毎日)
以前は科目Bの点数が足らずに不合格だったので、今回は科目Bの学習に重点を置いて学習していきます。
使用する参考書は『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者[科目B]第4版 (EXAMPRESS)』
学習記録
学習進捗記録(科目A・科目Bテキスト)
2025/07/09 科目A:1章(~P.46)
科目A:基礎理論①
2進数、基数変換(2↔️10↔️16)、2進数の四則演算
※定期的に計算問題を解けば問題なし。
2025/07/10 科目A:2・3章(~P.103)・科目B:文法(~P.57)
科目A:基礎理論②
ベン図と論理演算、論理回路、オートマトン(状態遷移図)、AI
※状態遷移図の問題は意味が分からなかったが、https://www.youtube.com/watch?v=c-Li4Pja9-A この動画を見て一発で理解ができた。◯が状態を表し、矢印は操作を表す。「受理される」の意味を理解しておらず要領が掴めていなかった。
科目B:文法(~P.57)
疑似言語の基本文法の習得と、トレースの演習。プログラム処理の理解は後回しで「とにかくトレース」を行うのが良いらしい。トレースをすると確かに着実に答えを導き出せているので安心感が高まっている。
2025/07/11 科目B:文法(~P.89)
科目B:文法
トレースの演習問題を中心に、実際の過去問にも取り組んだ。「落ち着いてトレースすれば解ける」という肌感覚を養えている気がする。今日は科目Aの学習ができなかったのは反省点。科目ABともに、欠かさず毎日行おう。
2025/07/12 科目A:4~6章(~P.233)科目B:1次元配列(~P.102)
科目A:4~6章
4章:コンピュータの構成要素 CPUや記憶装置について
5章:システムの構成要素 システムの分類(処理・構成・性能)
6章:ソフトウェア OSやジョブ、データ管理、ファイルシステムなど
科目B:1次元配列
一番シンプルな1次元配列の学習。トレースは引き続き心配なくできている。
トレースする前に暗算で処理が分かる場面も時々ある。
振り返り
巻末の単語チェックを見ながら復習を取り入れ始めた。寝る前の10分を毎日費やしたい。
2025/07/13 科目A:6章~11章(~P.436)科目B:1次元配列(~P.119)
科目A:6章~11章
7章:ハードウェア
8章:ヒューマンインタフェースとマルチメディア
9章:データベース 実務利用もあるので流し読み
10章:ネットワーク 伝送速度、サブネットマスクなどで計算あり。英略単語も多数。
11章:情報セキュリティ 共通鍵・暗号鍵はスキップ。のちほど動画学習で補う。
科目B:1次元配列
1次元配列の演習問題に取り組んだ。トレースせずに解釈で解ける問題がほとんどだった。実際の問題では単純な問題は出ないはずなので、テスト前は難易度高めの問題に絞って繰り返そう。
振り返り
日曜日でまとまった学習時間がとれた。科目Aを早く網羅したいという焦りがあって少し雑になっている。
科目Aテキストのスマホアプリを見つけた。スキマ時間を活用して過去問に触れよう。
2025/07/14 科目A:12章~14章(~P.495)科目B:2次元配列(~P.126)
科目A:12章~14章
12章:システム開発 テストケース数問題。
13章:ソフトウェア開発手法 アジャイル、ウォーターフォール。
14章:プロジェクトマネジメント PM職として根幹となる単元。
科目B:2次元配列 配列の難易度は易しく感じている。
振り返り
学習時間が十分とれなかった。朝に頭を使う学習を詰め込もう。
2025/07/15 科目A:14章~16章(~P.557)科目B:2次元配列(~P.147)
科目A:14章~16章
14章:プロジェクトマネジメント
15章:サービスマネジメントとシステム監査
16章:システム戦略
科目B:2次元配列 難しい問題が増えてきた。
2025/07/16 科目A:16章(~P.565)
科目A:16章:システム戦略
振り返り
毎日継続学習が途切れそうになった。脳の記憶を活かすためにも毎日継続は欠かさないようにしよう。
科目Aは苦手な計算単元はほとんど把握できており、残りは単語暗記がメインとなっている。
科目Bは難しい問題が増えてきて、さくっと理解できない時のストレスを乗り越える必要がある。
テキスト進捗率は科目Aが75%、科目Bが50%。
2025/07/18 科目A:16章~20章(~P.647)
16章:システム戦略
17章:システム企画
18章:経営戦略マネジメント
19章:ビジネスインダストリ
20章:企業活動
振り返り
記録が途切れていたが科目Aを中心に進めた。
科目Bは朝の学習時間を確保できず取り組めていない。
2025/07/22 科目A:21章(~P.703)読了
21章:法務
振り返り
科目Aを一通り読み終わった。予定より2日オーバーだが休日で取り返したい。月末までに苦手単元を繰り返し見直して過去問演習を行う。科目Bは受験日までの朝時間を充てて継続的に取り組む。
2025/07/23 科目A:弱点克服
復習:基数変換
科目Aテキストの読み直し後、過去問に取り組んで知識定着を促した。
2025/07/26 科目B:(~P.160)
振り返り
科目Aはスキマ時間でスマホアプリの一問一答やテキスト巻末の語句確認を見る程度。
科目Bは理解に時間をかけすぎる問題がある。
2025/07/27 科目B:(~P.194)
科目B:ありえない選択肢・再帰・オブジェクト指向
選択肢問題のテクニックである「消去法」の解説あり。短時間で正解の候補を選べるのでとても良き。
再帰は有名なユークリッドの互除法などを扱った。難易度易しめ。
オブジェクト指向は参照先を順番に追うのが大変。複雑度高め。
2025/08/03 科目B:() 、過去問道場
8月に入った。これから過去問を解く。復習まで含めて「3日に1回分」のペースを目安に解いていく。
科目Aは朝・晩とスキマ時間で着実に。短時間でも必ず毎日触れる。
科目Bテキストはまだ終えてないので、理解もほどほどに「5日以内(08/08まで)」を目安に一周終わらせる。
試験結果(8/30更新予定)
おたのしみに。
おまけ
【最新】効果的な記憶術
リトリーバル
リトリーバルと呼ばれる、学んだ内容を能動的に思い出す行為。例えば教科書を読んで、その後閉じます。そして白い紙に学んだ内容を書き出します。こうすることで能動的に自分の頭の中から情報をアウトプットします。記憶はインプットと思われがちですが、記憶力を高めるにはアウトプットが重要だそうです。